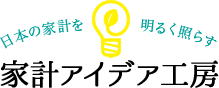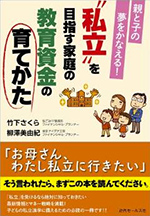- コラム
2025年4月からさらに充実! 子育て支援制度6つのポイント
【1】妊娠すると5万円!(妊婦のための支援給付)
妊娠中の女性を支援するための給付です。令和4年の補正予算でできた出産・子育て応援給付金を法制度化。流産・死産だった場合でも給付が受けられるようになりました。給付は2回。申請方法はお住まいの自治体ホームページを確認してください。
・妊娠届出時に5万円
・妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円
【2】こども誰でも通園制度(全国実施は2026年度)
保育所等に通っていない0歳6カ月から 満3歳未満のこどもが 時間単位等で柔軟に利用できます。2025年度は一部の自治体のみ実施で、全国実施は2026年度からになります。
・子ども1人あたり10時間/月
【3】両親ともに育休取得で「手取り10割」に
出生後休業支援給付が創設されました。 子の出生直後の一定期間内に 両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、 「休業開始時賃金日額×休業期間(28日が上限)×13%」の出生後休業支援給付金が、パパにもママにも支給されます。
産後パパ育休を取ったときに給付される「出生時育児休業給付金」も、ママが育休中にもらえる「育児休業給付金(休業開始から通算180日)」も支給率は67%。出生後休業支援給付金と合わせると、休業前の給与の80%相当額となります。給与の手取りは額面の80%程度ですから、最大で28日間はパパもママも手取り10割になるというわけです。ちょっとややこしい説明になりましたが、子どもが生まれる、または出産予定日からパパが産後パパ育休を取得すれば、パパもママも最大28日間、休んでいるのに休む前の収入を確保できることになります。パパの育児参加を円滑に行うためにも、産後パパ育休の取得は検討する価値があるのではないでしょうか。
【4】時短勤務時に賃金の10%を支給
育児時短就業給付を創設。こどもが2歳未満の期間に時短勤務で賃金が低下した場合、 時短勤務時の賃金の原則10%を支給するものです。
【5】残業免除が請求できる期間の拡大
育児・介護休業法の改正により所定外労働の制限(残業免除)の請求できる期間が、こどもが3歳になるまでから「小学校就学前まで」に引き上げられました。
【6】子の看護休暇の対象期間が延長されます
育児・介護休業法の改正により「子の看護休暇」の見直しが行われました。対象となるこどもの年齢を 小学校就学前から「小学校3年生修了時まで」に引き上げられています。 子の看護休暇は、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日取得可能となる休暇です。子の病気、ケガ、予防接種、健康診断で使うことができるものですが、今回の改正でさらに、感染症に伴う学級閉鎖や入園(学)式、卒園式にも使えるようになっています。なお、看護休暇は1日単位または時間単位で取得可能ですが、有給扱いになるか否かは勤務先により異なります。無給とする会社が多い状況ですので、確認した上で利用しましょう。